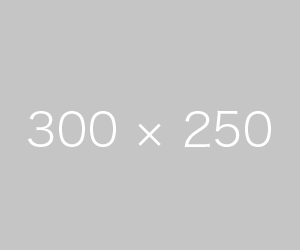前回自責点について語ったところ、その数日後の試合で、柳田選手の「千賀が悪い」発言により、自責点が話題になりましたね。結果としてタイムリーな話題となりました。
さて、前回に引き続きマインドちっくな話です。
皆さんは、もしプロの選手と話をする機会に恵まれたとしたら、何を聞きたいですか?「変化球の投げ方」とか、「勝負強い打撃の秘訣」、「打球の飛距離を伸ばすコツ」などでしょうか?
私は主に投手が専門ですが、もしプロの投手と話ができる機会に恵まれたら、必ず1つこれは聞こうというものを決めています。
それは「調子が悪いと感じた時に、何を考えて投げているか?」です。
調子がいいときは、極論を言えば、何も考えなくても案外どうにかなったりするので、仮に質問したとしても、あまり参考にならないかもしれません。
ただ、安定して結果を残したいのであれば、調子が悪いときの思考法は一流の人から絶対に聞いておくべきです。
私はそもそもたいした投手ではありませんでしたが、調子が悪い時は殊更どうしようもなく、マウンドで為す術もなく大量失点を食らう、、、ということもザラでした。
一方、プロの世界は、体調不良などは別として「今日は調子が悪いから投げられません」なんて言ったらすぐに出場機会を失う世界(だと思います。)
特に中継ぎ投手は、調子によって結果の波が激しければ、仕事にならないはずです。
勿論、調子が悪くても投げられるように、技術的な準備もしているはずですが、それは今の時代、ネットで調べれば結構ヒントは出てくるものです。しかし、私が知りたい「何を考えて投げているか?」というマインド面については、本人から生の声として聞かないと、なかなか知ることができません。
学生時代、当時解説者をされていた工藤公康さんの講演会に参加することができたのですが、質疑応答の時間があったにも関わらず、イモって質問することが出来ませんでした。(笑)
やはり、「やらなかった後悔」は、ずっと引きずるものです。
それ以来、プロの選手と話をすることができた時には、必ず聞くようにしています。
先日も、元プロの投手の方と話をする機会に恵まれましたので、質問してみたところ、その方は大きく2点をおっしゃっていました。
1.スコアラーにいただいた相手打者のデータを基に、相手打者の攻め方に集中する
2.その日はスピードの概念を捨て、投球としては球の出し入れにのみ集中する
1.について、
調子が悪いと感じてしまったら、どうしても意識が自分自身に向きがちです。そこで、相手打者の攻め方に集中することで、半ば強制的に意識を自分の外に向けることができる。効果的な意識転換だと思います。
2.について、
「スピードがないと抑えられない」という固定観念があると、なかなかこの考え方はできません。また、この考え方を誤解して、ただ置きにいって結局打ち込まれる、、、ということにならないよう、普段の練習から「調子の良し悪しに関わらず、球の出し入れはある程度思い通りにできる」という意識を持つことが重要ではないでしょうか。
この話を聞いた時、私は2018(平成30)年の春季リーグ開幕戦を思い出しました。
昔の話なので、既に卒業している学生の名前なども出してしまいますが、ヤフオクドーム(現・PayPayドーム)で行われた開幕戦の先発マウンドに立ったのは当時4年生の岡 泰成でした。
冬場の調整が順調に進み、開幕戦では常時140キロ台で投げられそうだと、本人も私も期待していました。
手応えを持って、意気揚々と上がったヤフオクドームの初回のマウンドでしたが、期待とは裏腹に、思ったよりも全然スピードが出ない。。。
我々も「あれ、ここまで出ないものか?」と不思議に思うくらいでしたが、本人にとっては、冬の手応えがあった分、尚更衝撃だったのではないでしょうか?
4年生の岡にとって、投手として登板する最初で最後のヤフオクドームのマウンドです。常人なら、もう少し意地になってスピードを追い求めても致し方無いところです。
ところが、初回のマウンドを終えた岡は、自ら「今日はスピードを捨てる」判断をしました。
結果として試合は1−3で敗れてしまったので、手放しでは褒められないのが残念ですが、岡も、リリーフで投げた松下も粘ってよく投げてくれたと思います。たいしたものでした。


※岡(写真上)松下(写真下)当時4年生の2人が奮闘した。
「ノーヒットノーランを達成した時は意外と調子が悪かった」という話はよく聞きます。調子が悪い時に「今日はもうダメだ」と諦めるのか、それとも知恵を振り絞り粘って投げるのか。マインド1つで結果が大きく変わることもあるということです。
あとは、投手についてもう1点言えるとすれば、
調子が悪い時に制球に影響が出る投手は、マインド以前の問題になってしまうので、
至急、普段の取り組みの見直しを行った方が良いでしょう。
351